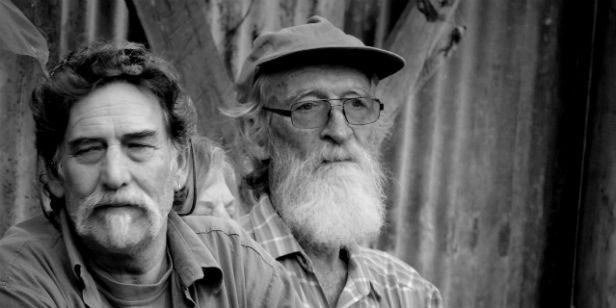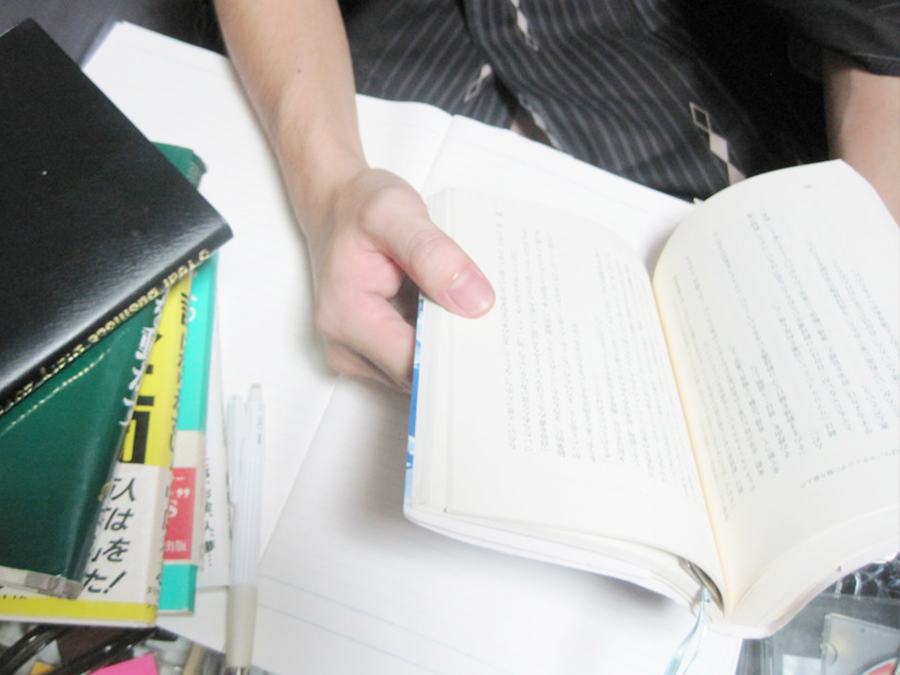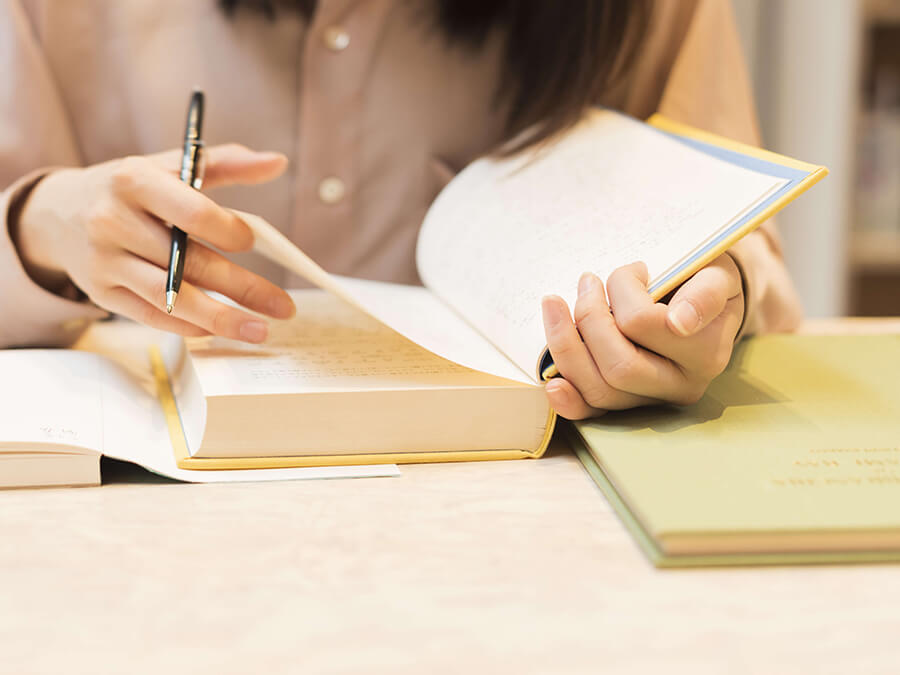特別養護老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、介護職員の活躍する現場はたくさんあります。
施設に入居する本人が考えるのは「人生の最期をどのように迎えるか」ということでしょう。多くの方が家族に迷惑をかけずに、旅立ちたいと考えているようです。対して家族は本人らしく最期を迎えてほしいと願っています。
日本の急速な高齢化を背景に、住み慣れた地域で人生の最期を送る「地域包括ケアシステム」や特別養護老人ホームを中心とした「看取り介護」に注目が集まっています。高齢者の看取りは医療という現場から介護現場に移りいく過程の中で、介護職員としてのスキルアップとは何か考えてみましょう。
高齢者の看取り介護
看取り介護とは終末期の方が人生の最期を迎えるまでの間に、本人の希望する日常を過ごせるようサポートする介護です。高齢者の方の多くには延命を目的とした医療を継続するより「自然に任せてほしい」と考えています。死を迎える場所は住み慣れたところがいいと希望する方も多く、入所者にとって住み慣れた施設で最期を迎えるのは理想だと言えるでしょう。入所者の家族に対する支援も、看取り介護の特徴です。
介護職員は家族に迷惑をかけたくないと思っている本人と、充実した最期を迎えてほしいという家族との気持ちを繋げる役割も果たします。高齢者の看取り介護施設は、本人の意向を尊重できる場として、期待が高まっています。
施設における看取り介護の流れ
高齢者の看取り介護は医療行為を必要とするのではなく、衰えを見守りながら本人や家族の戸惑いを軽減したり、食事をおいしく食べたりその人らしい生活を支えることです。看取り介護の流れを見ていきましょう。
入所期
看取り介護は本人意向を尊重した死を叶えるため、入所者の状態を確認したり、本人や家族の要望を聞いたりしてどのように看取り介護を進めていくかを話し合います。施設に入所が決まり次第、新たな人たちとの交流や施設生活に慣れる期間です。
安定期
本人の健康状態チェックや身体のケアを行い、ストレスを軽減しながら日常を過ごしてもらいます。最期を迎えるにあたってどのように過ごしたいかを模索したり、希望を聞いたりして自分らしい最期を送るための準備をします。
不安定/低下期
身体が衰弱する時期です。身体の状況に今後どのような変化があるのかを、本人や家族に伝えます。今後の生活の変化を予測し、具体的な介護計画を立てていきます。
看取り期
手を尽くしても改善が見込めない時期です。家族から看取り介護計画への同意をもらったり、本人と合いたい方に連絡をしたりします。最期の瞬間にはできるだけ家族に同伴をしてもらうよう手配をしたり、葬儀や今後の対応について相談を受けたりします。
看取り後
医師に死亡診断書を書いてもらい、事前に本人や家族に同意を得た手順でご遺体のエンジェルケアに入ります。その後、ご家族で葬儀社が決まっていなければ葬儀社の確保もサポートします。
家族葬についはこちらのサイトをご参照ください。
≫家族葬とはどういう葬儀?どこまで呼ぶ?費用や注意点とは?|葬儀・お葬式なら【公益社】
看取り介護のポイント
看取りの介護の内容やポイントについて見ていきましょう。
栄養と水分の介助
食事や水分補給を介助します。看取りの食事は栄養を蓄える食事ではありません。本人がおいしいものを食べたい時に食べてもらうようにしましょう。体調によっては呼吸が苦しい方もいます。相手の食べるペースに配慮しながら、食べたり飲んだりしてもらいましょう。
清潔
朝晩の洗顔や入浴、口腔ケアなど身体を清潔に保つための介助です。入浴を楽しみにしている方には負担のないように入浴の手助けをします。入浴が難しい方は身体を拭いてあげたり、手浴や足浴を準備したりします。最期まで清潔で気持ちよく過ごせるように心がけます。
苦痛の緩和
身体的、精神的な面の緩和をサポートします。終末期は熱がでたり全身がだるくなったり、身体的な苦痛を伴います。楽な体位を工夫してあげたり、手足を温めて血液循環を促したりできるだけ苦痛が和らぐようしてあげましょう。死を迎える恐怖から本人は、感情の起伏が激しくなりがちです。声かけをしてコミュニケーションをとったり、マッサージをしてスキンシップをとったりすると、本人も気持ちが落ちつくでしょう。
死亡時の援助
24時間以内に死が予想される場合、医師やご家族に連絡をします。危篤時の兆候が現れたら、本人に声をかえたり家族へのアドバイスをしたりしましょう。ご家族それぞれに最後の接し方で迷いがあり、本人に対する対応は違いますが介護職員として見守ってあげましょう。
介護職員の心の準備
入所者の状態により、一般の介護と異なる視点が必要になります。通常の介護では健康を考えて、入浴介助をしたり食事の量を調節したりしますが、看取り介護では本人やご家族の意向を尊重する介護です。「こんなことしていいの?」と思うような現場に携わりますが、回復や改善を見込んでいるわけではなく、苦痛を取り除き最後まで本人らしくいてもらうための介護だということを忘れてはいけません。
死と向きあっている本人やご家族を親身になって支えている介護職員にも、精神的負担はかかります。過ごしていた期間は短くても入所者さんの死を目の当たりにして、虚無感を感じる介護職員の方は多くいるでしょう。特に人の死に直面する機会が少ない若手介護職員の場合は死を受け入れる心の準備ができていないため、看取り介護の目的を認識し死を受け入れる心の準備が必要です。
施設の介護職員同士が一丸となり、チームで支え合うことが大切です。介護職員同士で疑問や課題の解決に対して声をかけ合い、1人で悩んでいる介護職員の孤独を防いでいきましょう。
看取り介護の課題
施設側の課題
看取り介護の視点はまだ明確な方向性がありません。施設側の都合や介護職員の思い込みによって取り組まれている可能性も少なくないでしょう。施設に配置される看護師の数も少ないため、介護職員が十分に研修を行えていない現状もあるようです。
そのため看取り介護を行うにあたって施設の明確な方針を軸にして、看取り介護を進めていく必要があります。
家族の理解
看取り介護は一般的な介護と違うところがあるため、家族に理解してもらえない対応があります。介護職員の説明により、家族に納得してもらって始めた看取り介護ではありますが「熱がでているのに病院にいかないの?」と疑問に感じる家族もいるでしょう。本人の状態と対応について介護職員より、しっかりと説明を受けて看取り介護への理解が必要です。
特別養護老人ホームを利用できる人
主に看取り介護をいっている特別老後老人ホームを利用できる方は、年金をもらっている高齢者が対象になります。高齢者の中には生活保護の方もたくさんいるのが現状です。年金もなく生活保護も受けていない高齢者の方々が看取り介護を受けられないのも社会的な課題と言えるでしょう。
施設に葬儀の依頼を受けた場合
超高齢化社会に伴い、国の方針は看取り介護に力を入れるようになりました。今までの施設は、体調が悪化すると救急車を呼ぶだけの対応で、他の入居者がパニックにならないよう配慮をするのが一般的です。
看取り介護が普及するにあたって施設側でも本人の死後、家族より葬儀の相談を受け提携している葬儀社に遺体を安置する流れとなっています。施設も死後の対応で依頼を受ける時には注意が必要です。本人の家族に納得をしてもらい、必ず同意を得た上で葬儀の段取りを受けましょう。故人の財産を扱うケースもあり、葬儀代が思ったより高かったと後から言われてトラブルになる可能性があります。施設の流れに任せて葬儀の段取りを組むのではなく、担当している家族としっかり打ち合わせをして進めましょう。