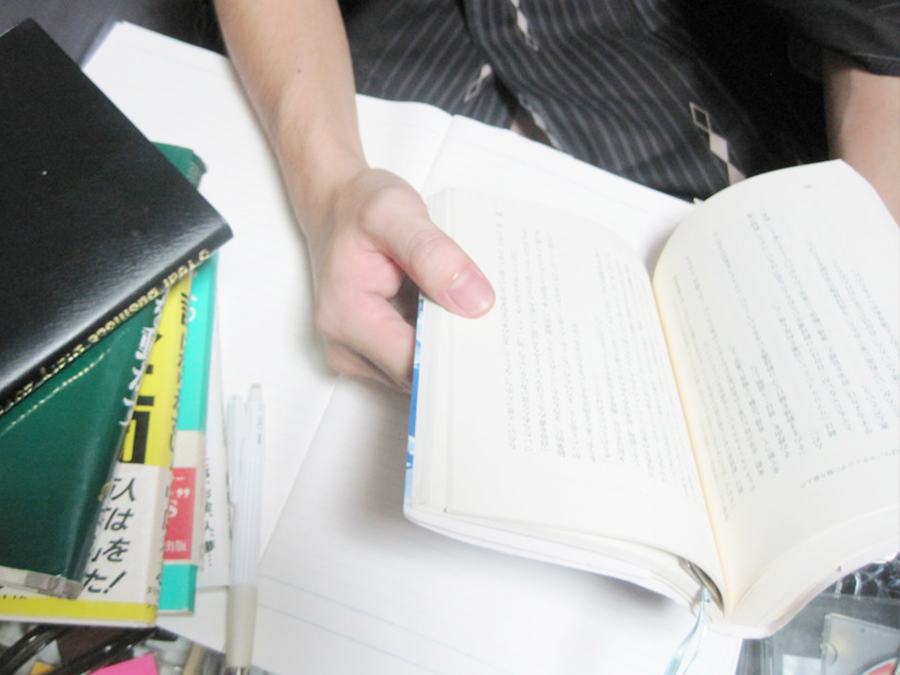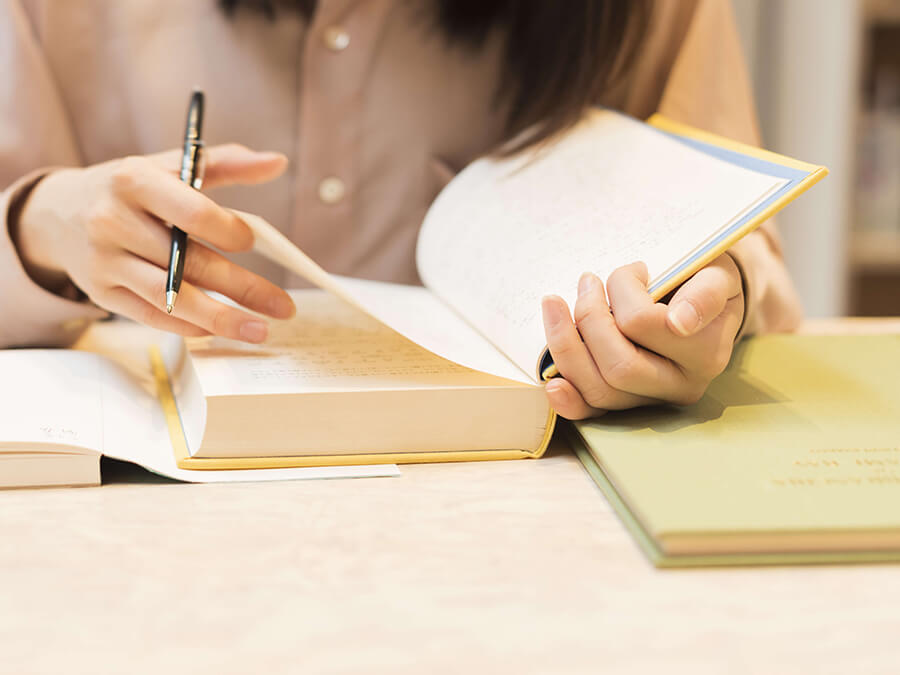超高齢化社会とは?
高齢者の人口割合が高い国や地域のことを高齢化社会と呼びますが、高齢化社会と超高齢化社会はどう違うのでしょうか。
国や地域などで暮らす総人口に対して、65歳以上の高齢者が占めるが割合のことを高齢化率と呼んでいます。
国連や世界保健機構(WHO)などでは、高齢化率が7%を超えた場合に高齢化社会、その倍の14%を超えた場合に高齢社会、7%の3倍に当たる21%を超えた場合に超高齢社会というと定義しています。
日本は1970年に高齢化社会となり、1994年に高齢社会になりました。さらに、2007年に高齢化率が21.5%となり、超高齢社会に突入しています。
今後も高齢化率は上がり続け、2025年には約30%、2060年には約40%に達する見込みです。
高齢化の現状とは
2017年10月1日時点で、日本の総人口は1億2,671万人に対し、65歳以上人口が3,515万人となり、総人口に占める割合が27.7%と推移しました。
それに対して15歳~64歳人口は1995年をピークに減少に転じ、2013年には1981年以来32年ぶりに8,000万人を下回りました。
2012年の推計と比較すると人口の減少と高齢化の進行度合いは緩和しています。
超高齢社会がかかえる問題とは
日本は高齢人口が短期間で増える中、医療福祉サービスが課題となっています。これまでの医療制度や保険制度では対応しきれないという状況が生じています。
また日本における家族構成についてみてみると、核家族化が進み、65歳以上の夫婦のみの世帯が増加しているのが現状です。都心部においては独居者が多く、介護できるものがいないということも。
高齢者が障害をかかえた場合には、自宅か施設での生活という選択が重要となります。
今の社会保障制度は、これからの未来を担う世代に問題を先送りしていると指摘される声も実際あります。高齢者と若者がともに納得し、不公平感のないシステムの実現が大きな課題となってきています。
地域で超高齢社会を支える
地域住民同士の関わりが減ったことで、絆の希薄化となり、孤立する方が多く見受けられるようになりました。その結果、孤独死が問題となっています。
こういった問題を解決するには、地域全体で支えていくことが必要とされています。
地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」
地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳を守りながら、自立した生活が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるようにした支援やサービス提供体制のことです。
団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年以降、医療や介護の需要が増加することが見込まれています。このため、厚生労働省では2025年を目途に地域包括ケアシステムの推進が行われています。