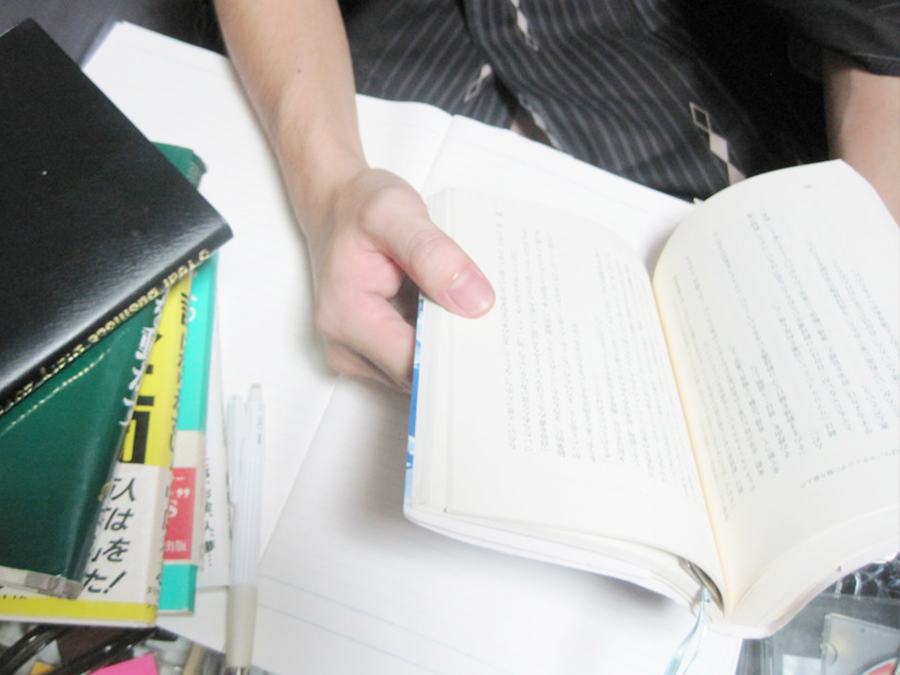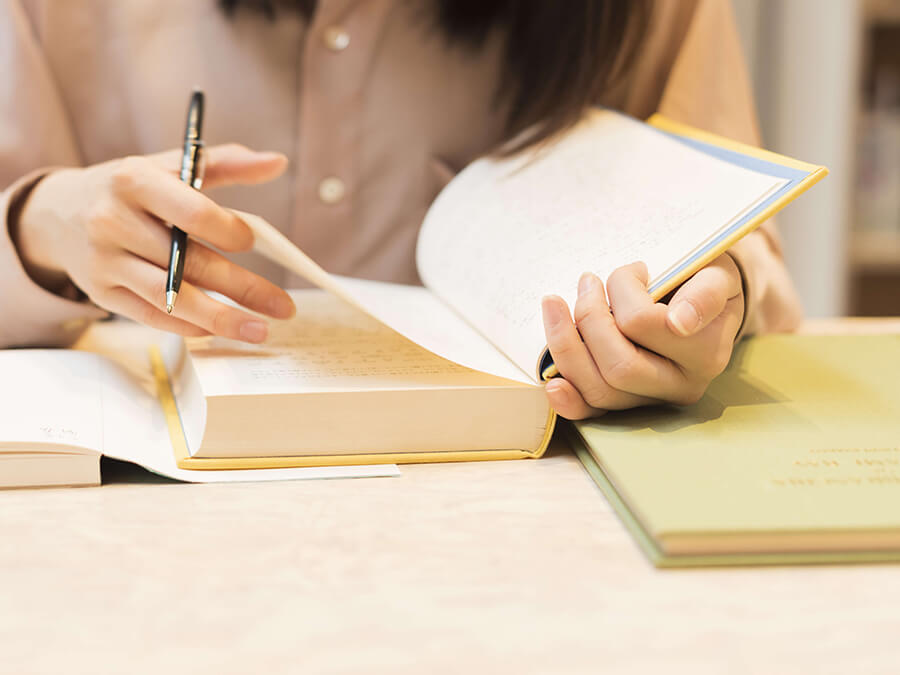要介護の原因1位は、脳血管疾患
高齢化が猛スピードで進む日本では、介護の問題は誰もが避けては通れない道だと覚悟しておく必要があります。
内閣府が発表した調査結果によると、2014年の日本の人口は1億2,708万人。
このうち、65歳以上の高齢者数は、過去最高の3,300万人となり、日本の総人口の26%が高齢者となりました。
また、戦後のベビーブームに生まれた団塊の世代が65歳に達した2015年には、高齢者数は3,395万人と急増し、団塊の世代が75歳になる2025年には3,657万人に達する見込みです。
高齢者のうち介護保険サービスを利用した人、2015年1月現在で488万4,000人となっており、このうち比較的軽度の要介護1~3の高齢者は自宅で介護サービスを受けている人が多く、重度の要介護5の高齢者の場合は、約半数が施設でサービスを受けています。
要介護となった原因を見てみると、最も多いのが脳血管疾患で約17.2%。次いで認知症(16.4%)、高齢による衰弱(13.9%)、骨折・転倒(12.2%)と続いています。
脳血管疾患は特に男性が多く、26.3%と高い割合になっています。
では介護をする家族についてはどうでしょうか。
要介護となった高齢者を介護する人は、配偶者が26.2%と最多で、次いで子どもが21.8%、子どもの配偶者が11.2%となっています。
性別で見ると男性が31.3%、女性が68.7%と圧倒的に女性が介護する割合が多いのが特徴です。
また、介護をしている人の平均年齢は男性が69.0%、女性が
68.5%と過半数が60歳以上となっており、多くの家庭が老々介護を行っていることがわかります。
介護の困難
これらのデータから分かるように、介護をする人も60歳を過ぎて体力的に自信が持てない年代であるケースが多くなっています。
このため親も子も、介護が必要となったときどうするかを、元気なうちから話し合っておくことがとても大切です。
というのは、近年では在宅での介護が一般的になりつつありますが、要介護度が高くなると、施設に入所して介護を受ける必要がある場合もあるからです。
しかし、介護施設は不足気味ですから、入所までに何年も待たなければならないケースは少なくありません。
いざというときに困らないように、今のうちからどのような介護サービスが利用できるのか、民間の介護施設を利用する際にはどの程度の費用が必要なのかなど、さまざまな情報を収集するなどして早め早めに準備をしておくことが大切です。
息子や娘がいるからいざとなったら頼りにできると安心している人も多いのですが、離れて暮らしているケースも多く、同居がむつかしくて家族の介護が受けられないなど、期待通りに行かないことも多いものです。
逆に、子どもが親孝行だと思って親の介護をしても、予想以上の負担の大きさに、親子の関係がギクシャクするケースもあます。
近年では、親の介護をする人が仕事と介護の両立ができずに長年勤めていた会社を退職するケースも目立ってきました。
(参考サイト)
在宅介護のお金と負担
家計経済研究所の調査によると、介護と仕事の両立で困難と感じることで最も多かったのが体力や気力が続かないで、男性の66.7%、女性の60.5%が体力・気力面での負担を感じています。
次いで仕事の質が下がった(男性61.9%、女性45.6%)、仕事を休みすぎる(男性34.9%、女性27.2)となっています。
また、男性の13.4%、 女性の27.6%が介護によって仕事を辞めた経験があると答えています。